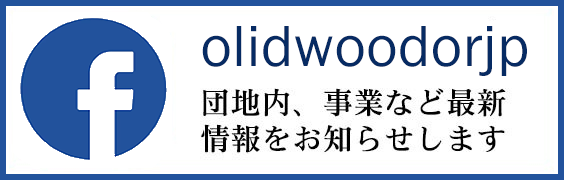桜といえば、「花見」。みなさんも花見にはいろいろな思い出があることでしょう。
私の場合、昔ある団体で関西の領事館の領事と交流する企画を命ぜられたことがありました。
私は英語は堪能ではないし、随分悩みましたが、桜の花見なら安上りで、家族づきあいがすぐに出来ると考えました。
一番心配した参加者も、米国、カナダ、フランス、ソ連、インド、インドネシアなどの国々の領事とその家族が参加してくれ不安だった進行も何のことなく、花より団子で同じ世代同士、おおいに盛り上がり、大変好評の結果となりました。
その延長でその年は家族会を十回近くも開き、翌年も花見の催促がありまた開催してしまったほどです。

このように、今まで交流したことのない人とも親しくなれる花見の場は、世界でも日本だけ。それぞれの国の人に聞いてもみんな自国にはない習慣とのこと。いろいろな文献を調べた結果、どうも日本固有の風習のようですね。 では、この花見の風習はいつからあるのでしょうか。古来より花見といえば、梅が中心だったことは記録や、すでに多くの文献などに書かれています。

平安時代中期ごろには梅から桜に変わりますが、まだ上流実社会にだけに許された文化で、酒を飲んで騒ぐようなものではありません。一般大衆に普及させたのは、江戸時代の八代将軍吉宗でした。吉宗は現代版カルロス・ゴーンに当てはまるかも知れませんね。
合理主義者であり、あらゆることを改革し、質素倹約を推し進めたことは有名で、そのため特に江戸では大衆のストレスはたまり、放火が多かったように不平が鬱積したといわれています。 ここで吉宗は、大衆のガス抜きと地域振興の一石二鳥の政策として、それまで貴族の楽しみだった花見を広く開放し、花見の場所周辺を整備し、花見では無礼講を推奨したのです。 当時の社会状況では女性は自由に出歩くことが出来なかったのが、この時期とこの地区では自由であり、男女の出会いの場でもあったようです。
またいろいろなニュービジネスが発生し、花見とともに全国に広がったというわけです。

桜の花は、たとえ一本であっても人を引き付ける魔力があるようですね。最近静かなブームになっている名木巨樹巡りでも、桜のすばらしさを満喫することができます。桜の寿命は他の樹木にくらべると短く百年くらいですが、巨樹となると千年以上のものも各地に存在します。
このブームの前にでも、作家の宇野千代さんは桜の老樹に魅せられ日本中に広めた人です。彼女は友人から岐阜県根尾谷にある樹齢1200年の桜の老樹が枯れ死寸前という話を聞き、見に行き、そこで出会った桜が、彼女のその後のライフワークとなったのです。
彼女はこの桜の巨樹を再び勢い返らせようと決心し、まず岐阜県知事に手紙を書き、この桜の状況を訴え、新聞社などにも広げました。その結果彼女の熱意に知事も動かされ、回復指示を出し、桜の巨樹は見事に回復しました。当時は桜を見に来る人もまばらだった場所が、今はその時期に20万人も訪れるそうです。この経緯は彼女の小説「淡墨の桜(うすずみのさくら)」に書かれ、ノンフィクションですが、主人公は本人、今の時代でも新鮮で面白い本です。

本当に桜という木は「不思議」につきます。何が日本人をここまで熱狂させるのか、その季節になると、テレピや新聞はもちろん、週刊誌やカメラ雑誌までもが桜、桜の連続。桜の花びらはいっせいに木に無数につき、樹木全体がひとつになる、そしてわずかな日にちで、ちいさな花びらにわかれていっせいに空中に散って、一時的にも視界をさえぎる。 万朶と咲いた昼間の木々も美しいですが、夜に帰宅するときに街灯に浮かぶ桜も、別世界の神秘さがあります。 梶井基次郎の短編に「桜の樹の下には屍体が埋まっている」というフレーズがありますが、なるほど、昼も夜も妖しいオーラを発してい